自動車発電の仕組みとは?メリット・デメリットや自作キット・蓄電グッズも紹介
自転車を漕いで電気を生み出す「自転車発電」は、身近なもので省エネを体験できる仕組みです。自分の体を動かして発電するので、電気を作る大変さが身をもって実感できるでしょう。自作キットを活用すれば、詳しい知識がなくても気軽に自転車発電を導入できます。
そこで本記事では、自転車発電とはどんな仕組みかについて解説します。自転車発電のメリット・デメリットや、自転車発電機の作り方も掲載しているので、オフグリッド生活が実現できるでしょう。自転車発電に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
自転車発電とは
自転車発電とは、自転車を漕いでダイナモを回転させて電気を得る発電方法です。子供が省エネを楽しく体験するためにも利用されています。実は、普段から使っている自転車のライトも、漕ぐ力で瞬間的に発電した電気で電球を点灯させているのです。
一般的な自転車発電では、発生した電気をバッテリーに蓄電します。特別な道具は一切いらず、体さえあれば発電できるので、省エネ生活や停電時に活用できるでしょう。
自転車を使って発電する仕組み
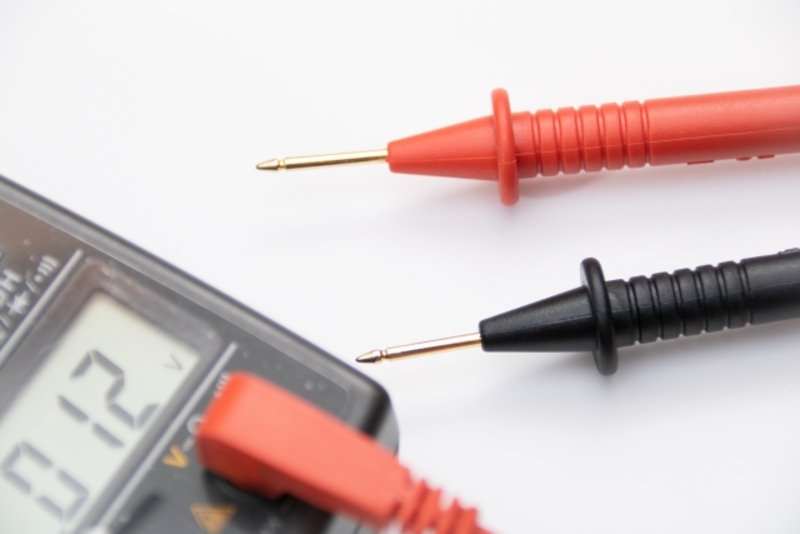
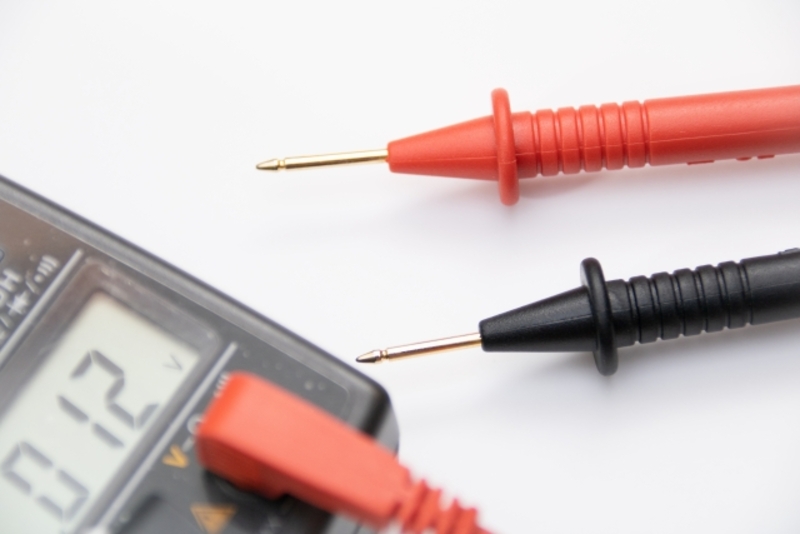
自転車発電は、タイヤやダイナモを回転させて得た電力をオルタネータに伝え、インバーターを経由して交流として電力を取り出す仕組みです。自転車を漕いで実際に電力を取り出すまでの流れを見ていきましょう(※1)。
自転車を漕いで交流を発生させる
交流を整流回路で直流12Vに変換する
直流12Vをオルタネータに入力して励磁する
オルタネータが発電を開始し、交流が発生する
オルタネータ内部で直流に変換される
直流をインバータに入力し、交流100Vに変換する
オルタネータで作られる電気は直流の12Vです。一般家庭で使われる電力は交流の100Vなので、インバータで電圧を変換する必要があります。
自転車発電の発電量はどのくらい?
自転車発電の発電量は最大で100W程度です。自転車のタイヤが発電機に接している面が小さい上に、人間の体力には限界があります。自転車を漕ぎ続けたとしても、生活に必要な電気を全ては賄えません。100Wの電力で動かせる電化製品の目安は、以下のとおりです。
ラジオ(20W)
スマートフォン(5W)
LED電球(15W)
テレビ(70W)
扇風機(50W)
ノートパソコン(40W)
発電量を増やしたい場合は、0.1Ω、5W以上の抵抗をつけてオルタネータ出力を並列に接続すると、複数台の自転車で発電できます。
自転車発電のメリット5選


人の力を利用した自転車発電は、地球に優しい発電方法です。エコや節電、教育、健康などの多方面でメリットがあります。自転車発電のメリットは、以下のとおりです。
メリット1|停電時に電化製品を動かせる
メリット2|脱炭素社会の実現に貢献できる
メリット3|電気代を節約できる
メリット4|健康増進の効果が得られる
メリット5|教育・趣味に活用できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
メリット1|停電時に電化製品を動かせる
自転車発電は、停電してコンセントからの電力供給が断たれた状況でも電気を生み出せます。災害による停電は3日以上続く場合もあり、その間は電化製品が一切使用できません。停電時に自転車発電が活躍する場面は、以下のとおりです。
LEDライトで夜の暗闇を照らせる
外部との連絡手段になるスマホを充電できる
扇風機や電気毛布で体温調節ができる
テレビやラジオから情報収集できる
普段から自転車発電で発電した電気を蓄電しておけば、いざという時に利用できます。
メリット2|脱炭素社会の実現に貢献できる
自転車発電は燃料を使わないので、環境への負荷がほとんどありません。発電時に排出される二酸化炭素は人の呼吸のみです。一方、日本の主な発電方法である火力発電では燃料を燃やし、地球温暖化の原因である大量の二酸化炭素を排出します。
2015年に採択されたパリ協定を境に、世界は二酸化炭素の排出量をゼロにする脱炭素社会へと進み始めました。自転車発電は、脱炭素社会の実現に貢献できる発電方法です。
メリット3|電気代を節約できる
自転車発電では、買電量を減らして電気代を節約できます。スマートフォンや照明器具、テレビなどの小型機器を自転車発電でまかなえば、月々の電気代を削減できるでしょう。
ただし、自転車発電を導入するためにはダイナモやオルタネータ、インバータなどを購入する必要があるため、ある程度の初期費用がかかります。大幅な節電効果は期待できないので、節電だけを目的に自転車発電を取り入れるのは現実的ではありません。
メリット4|健康増進の効果が得られる
他の再生可能エネルギーとの大きな違いは、健康増進の効果が得られる点です。自転車を漕ぐ作業は有酸素運動なので、運動不足が解消され、以下の効果が得られます。
生活習慣病の予防になる
体力や持久力がつく
運動器疾患のリスクが軽減する
心肺機能が高まる
自己効力感が高まる
ストレスが発散される
電力を生み出しながらダイエットもでき、まさに一石二鳥の発電方法です。
メリット5|教育・趣味に活用できる
自転車発電は、電気の基礎や発電の仕組みを学習するのにぴったりな教材です。電力計を使って発電した電力量を測定できれば、身近な電化製品を動かすのにどれだけの時間と労力を要するのかが身をもって体験できます。
また、運動不足を解消できるので、趣味にしてみるのもおすすめです。普段からロードバイクが趣味な方は、発電機を取り入れて楽しみながら省エネに貢献しましょう。
自転車発電のデメリット5選


人の体さえあれば発電できる自転車発電ですが、メリットばかりではありません。普段使いするにはあまりに非効率で、後悔につながる可能性もあります。
自転車発電のデメリットは、以下のとおりです。
デメリット1|発電効率が悪い
デメリット2|体力的に長時間の発電ができない
デメリット3|高出力家電は動かせない
デメリット4|出力が安定しない
デメリット5|自転車を置くスペースが必要になる
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
デメリット1|発電効率が悪い
電化製品を動かすにはペダルを漕ぎ続けなければなりませんが、人間の体力は有限です。人間が費やす労力の割に得られる電力が少なく、発電効率は悪いと言えるでしょう。
そのため、普段使いには向いておらず、緊急時の非常用電力としての使い道が得策です。大きな電力を得るためには、ソーラーパネルと併用する必要があります。
デメリット2|体力的に長時間の発電ができない
人間の体力には限界があるので、長時間の発電ができません。特に消費電力が比較的高い電化製品を動かす場合は、短時間でも大きな負担になります。一度体力を消耗したら、ある程度回復するまで休む必要があるので、電化製品は断続的な稼働になるでしょう。
デメリット3|高出力家電は動かせない
自転車発電で動かせる家電の消費電力は100Wが限界です。スマートフォンや扇風機、ラジオなどは動かせますが、日常生活で頻繁に使用する以下のような家電は動かせません。
冷蔵庫(150W)
炊飯器(350W)
洗濯機(500W)
エアコン(1,000W)
掃除機(1,000W)
ドライヤー(1,100W)
電子レンジ(1,300W)
デメリット4|出力が安定しない
継続的に発電するためには、発電機の回転数を一定に保つ必要があります。人間の体力は有限なので、常に同じペースで自転車のペダルを漕ぎ続けるのは不可能です。
その結果、出力が安定せずに、電化製品は断続的な運転になるでしょう。安定性が要求される医療機器や精密部品を内蔵した電子機器の稼働には、向いていません。
デメリット5|自転車を置くスペースが必要になる
自転車発電ならではのデメリットといえば、広い設置スペースが必要になる点です。マンションやアパートなどの限られた住環境では、自転車を設置すると生活空間が圧迫されてしまいます。未使用時は、自転車を置けるだけの収納スペースも必要です。
関連記事:パススルー充電とは?ポータブル電源で機能を使うメリット・デメリットも解説
関連記事:弱電とは?強電との違いや弱電設備工事に必要な資格・強電との離隔も解説
自家発電した電気を蓄電できるポータブル電源とは


自転車発電では瞬間的に最大100W程度の電力しか発電できません。人間の体力には限界があるため、安定した出力は期待できないでしょう。また、自転車を漕いでいる状態で操作できる家電は限定されてしまいます。そこでおすすめのアイテムが、ポータブル電源です。
ポータブル電源とは、内部のバッテリーに大量の電気を蓄電し、コンセントを経由せずに電化製品を動かせる機器を指します。自転車発電や太陽光発電で発電した電気をポータブル電源に貯めておけば、好きなタイミングで電力を使用できます。
自家発電とポータブル電源を組み合わせるメリットは、以下のとおりです。
消費電力が1,000Wを超える家電も動かせる
発電した電力をその場で使い切る必要がない
発電と給電を同時に行う必要がない
複数の電化製品を同時に動かせる
家電の使用時は安定した出力を維持できる
多彩な出力ポートから家電に給電できる
屋外に持ち出して電化製品に給電できる
自転車発電機を屋外に持ち出すのは難しいですが、発電した電気をポータブル電源に蓄電しておけば、ポータブル電源のみを屋外に持ち出して家電が動かせます。自転車発電よりも発電効率の良いソーラーパネルとの組み合わせがおすすめです。
自家発電に必要な性能|おすすめの製品
自家発電で使用するポータブル電源は、用途に合わせて容量を自由に拡張できるタイプが重宝します。自転車発電で生み出した僅かな電力を貯めておくだけなら、250Wh程度の容量があれば十分です。一方、太陽光発電を行う場合、800Wh程度は必要になるでしょう。
EcoFlowは、ワイヤレス接続で容量を拡張できるポータブル電源「RIVER 3 Plus」を販売しています。業界初となるGaNテクノロジーを搭載し、自転車発電の最大発電量である100W以下の電化製品の稼働時間を2倍に延長しているのが特徴です。
「RIVER 3 Plus」の主な特徴を見ていきましょう。
定格出力600W、X-Boostで最大900Wの家電を動かせる
容量を286Whから858Whまで拡張できる
AC出力ポート2口は背面にあり、使用時にケーブルが気にならない
30dB以下の静音設計により、就寝時も使用できる
LiFePO4セルを採用し、10年以上も活躍する
停電時は10ms以内に電力を切り替える
防水性、耐火性、耐衝撃性に優れている
本体にはライトが内蔵されており、停電時の照明代わりにもなります。自家発電を取り入れて、オフグリッドを実現したい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。
初心者必見!自転車発電機の作り方・手順


自転車発電は、普段使っている自転車でも発電機を取り付ければ実現できます。主に必要な材料は、自転車、ワークスタンド、ダイナモ、整流回路、オルタネータ、インバータです。その他にも、各機器を接続するための細々とした部品を用意する必要があります。
自転車発電機の作り方は、以下の手順です。
手順1|L字金具・オルタネータを固定する
手順2|ダイナモを取り付ける
手順3|各端子を接続する
手順4|キャパシタをつなげる
手順5|電力取り出し用の電線を接続する
手順6|シガーソケットにインバータを差し込む
それぞれの手順について、詳しく見ていきましょう。
手順1|L字金具・オルタネータを固定する
まずは、自転車をワークスタンドにのせ、タイヤの位置に合わせて木製ボードを設置します。オルタネータのプーリーがタイヤに接触する場所を見つけ、印をつけましょう。
ボードは回転で後方に力がかかるため、後ろを長めに設計すると安定します。印に合わせてL字金具を木ねじで固定し、120mmのボルトで取り付けます。金具や取り付け方は、オルタネータの形状に応じて工夫してみてください。
手順2|ダイナモを取り付ける
励磁用電力を作る自転車用ダイナモの位置は、レバーを起こした状態で仮決めしましょう。使用時にレバーを倒すとタイヤに接触する場所が理想的です。
自転車が変わると位置調整が必要になるため、長めのアングルに取り付けて移動可能にしておきましょう。まずはアングルに固定してからダイナモを固定するとスムーズです。
手順3|各端子を接続する
続いて、以下の手順で自転車用ダイナモやレギュレートレクチファイアの配線を作ります。
ダイナモの端子から電線を抜き、新しい赤・黒(白)電線をオルタネータまで届く長さで延長し、平型端子を取り付ける
レギュレートレクチファイアの端子と同じ大きさの端子を使い、赤はプラス、黒(白)はマイナスに接続する
レギュレートレクチファイアからオルタネータへ電線を配線し、赤はB端子へ、黒(白)はボディのネジ部へ固定する
短い赤電線を加工してB端子とIG端子を接続する
※オルタネータ入手時にコネクタ類もあれば作業が容易になります。
手順4|キャパシタをつなげる
キャパシタの端には、丸形端子または鍬形端子を取り付けます。次に、キャパシタのプラス側(赤い電線)をオルタネータのB端子に接続します。
B端子には、すでにレギュレートレクチファイアのプラス端子やIG端子とB端子をつなぐ端子が接続されているはずです。さらに、キャパシタのマイナス側(黒い電線)は、オルタネータのボディにあるネジ部に固定します。ネジを緩めて取り付けましょう。
手順5|電力取り出し用の電線を接続する
オルタネータで作った電気を取り出すため、十分な長さの電線を用意します。一方には丸形端子か鍬形端子を、もう一方にはシガーソケット用にギボシ端子を取り付けてください。
電力取り出し用電線のプラス側(赤い電線)はオルタネータのB端子に接続し、B端子には他の端子と合わせて計4つが集まります。電力取り出し用電線のマイナス側(白い電線)はオルタネータのボディにネジで固定し、発電中に外れないようしっかり締めましょう。
手順6|シガーソケットにインバータを差し込む
電力取り出し用電線のキボシ端子を、シガーソケット側にも取り付けます。接続向きを間違えるとインバータが故障するため注意してください。B端子からの赤い電線はシガーソケットのプラス側、ボディからの黒い電線はマイナス側に接続します。
キボシ端子はかしめる前にチューブを通しておくのを忘れないようにしましょう。最後にシガーソケットにインバータを差し込めば完成です。
自転車発電機は自作キットで簡単に製作できる


ダイナモやオルタネータ、インバータなどの部品を集めて、1から自転車発電機を自作するのは、大変に感じる方も多いのではないでしょうか。部品一式と製作マニュアルが同梱した自作キットを活用すれば、専門知識がない方でも気軽に自転車発電機が作れます(※2)。
製作に要する時間は、3時間ほどです。組み立てにはハンダやプラスドライバ、ニッパ、ペンチなどの工具が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
まとめ


本記事では、自転車発電の仕組みについて解説してきました。
自転車発電は、自転車を漕いでダイナモを回転させて電気を生み出す発電方法です。自転車発電では最大100W程度の電力を発電できるので、スマートフォンや扇風機、テレビなどの小型家電に給電できます。複数台の自転車を並列接続すれば、発電量の増幅も可能です。
自転車を漕ぐ作業は有酸素運動になるので、発電と同時に健康増進の効果が得られます。ただし、発電効率が悪く、出力が安定しない点に注意しましょう。
EcoFlowは、自転車発電や太陽光発電で生み出した電気を蓄電するのに最適なポータブル電源を販売しています。自家発電を導入したい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。