弱電とは?強電との違いや弱電設備工事に必要な資格・強電との離隔も解説
私たちが普段使用している電気は、電圧の違いから「弱電」と「強電」の2種類に分かれます。弱電は電話やインターネットなどで信号を送るために用いられ、強電はモーターやエレベーターなどを動かすために用いられるのが特徴です。
そこで本記事では、弱電や強電とは何かについて解説します。弱電設備と強電設備の具体例や、弱電と強電を隔離すべき理由も掲載しているので、弱電と強電の違いを完全に理解できるでしょう。両者の接触を防いで安全に電気を扱いたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
弱電とは|信号として利用
弱電は、電気を信号として利用する場合に用いられます。情報の伝達や制御が目的なので、物を動かせるほどの大きな電力はありません。そのため、小容量・小電圧で発電や感電の心配がなく、安心して使用できるでしょう。
電技や内線規程では電圧についての定義がありませんが、規程内に記載のある小勢力回路は60V以下に降圧された回路を指します。60Vの使用電圧は48V以下しか存在しないため、弱電は48V以下と捉えられるのです。
強電とは|エネルギーとして利用


強電は法令や内線規程で定義されておらず、弱電の対義語として使用されます。強電の使用電圧は100V以上です。弱電は情報を伝達するのに対し、強電は動力やエネルギー源として使用されます。強電の主な種類は以下の4つです。
種類1|低圧
種類2|高圧
種類3|特別高圧
それぞれの種類について、詳しく見ていきましょう。
種類1|低圧
低圧は交流で600V以下、直流で750V以下の電圧です。家庭用のコンセントや工場の機械類などに使用されます。電化製品に高圧がかかると機器が故障するだけでなく危険を伴うので、家庭に流れる電圧は低く変電されているのです。
種類2|高圧
高圧は交流で600V~7,000V、直流で700V~7,000Vの電圧です。電柱につながれている配電線に使われており、家庭や工場に電気を送るためには高い電圧が必要になります。配電線に人間が直接手を触れると感電し、死亡事故につながる危険もあるのです。
種類3|特別高圧
特別高圧は7,000V以上の高い電圧です。発電所から変電所に電気を送る際に使われ、数十万Vに達することもあります。大容量の電気を効率よく送るためには、非常に高い電圧が必要です。山岳地に設置された鉄塔を経由して送電されます。
弱電と強電の違いを比較


弱電と強電の主な違いは、以下のとおりです。電圧や用途で明確に分かれます。
弱電 | 強電 | |
使用電圧 | 48V以下 | 100V以上 |
用途 | エネルギー源 | 信号の伝送媒体 |
理論 | 電気工学 | 電子工学 |
一昔前までは、電気を弱電と強電に分けて使用される機会が多くありました。しかし、現在では弱電や強電を単体で主体とする設備やシステムはほとんどありません。強電と弱電の技術が絡み合った設備やシステムが主流です。
弱電設備と強電設備の具体例
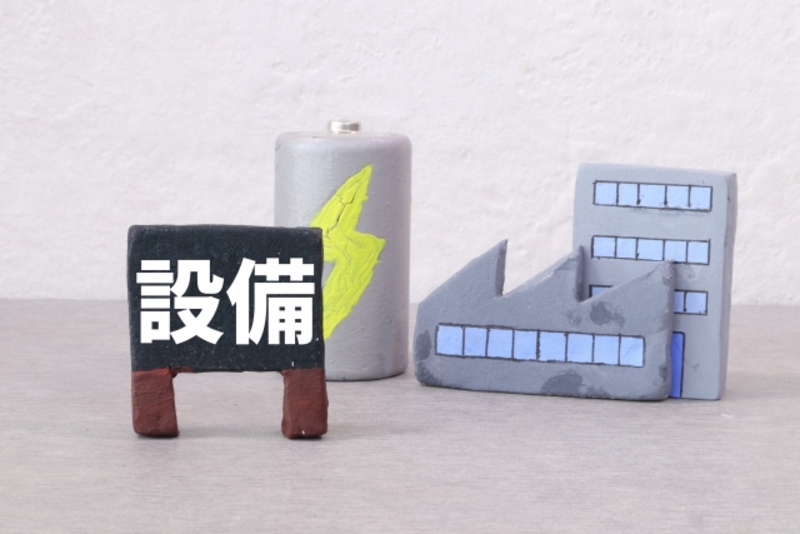
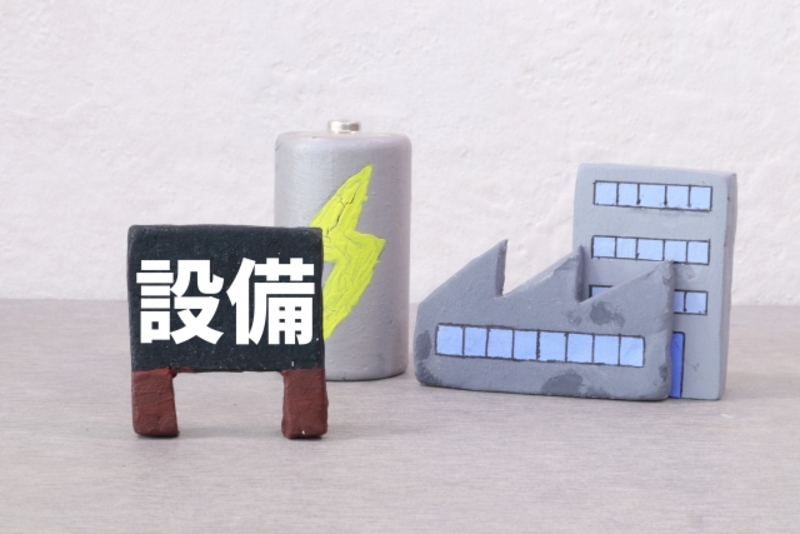
身の周りにある電気設備は、弱電設備と強電設備に分けられます。弱電設備工事はネットワークや電話線の工事を指すのに対し、強電設備工事は建設設備を稼働させるのに必要な電気設備の工事です。弱電設備と強電設備の具体例を紹介します。
弱電設備とは|LAN設備・放送設備等
強電設備とは|電灯設備・動力設備等
それぞれの具体例について、詳しく見ていきましょう。
弱電設備とは|LAN設備・放送設備等
弱電設備とは、信号や通信の伝達を目的とした電気設備です。一般家庭やオフィス、工場など、建物の規模を問わず導入されています。弱電設備の具体例は、以下のとおりです。
通信設備
放送設備
監視カメラ
LAN配線
信号制御設備
セキュリティシステム
インターホンやネットワーク機器なども弱電設備に該当します。
強電設備とは|電灯設備・動力設備等
強電設備とは、高い電圧でエネルギー源となる電気設備です。電灯設備や動力設備などとして、身近なところに存在しています。強電設備の具体例は、以下のとおりです。
電灯設備
動力設備
受変電設備
幹線設備
自家発電設備
避雷設備
照明やエアコン、エレベーター、変電設備なども強電設備に該当します。
弱電設備工事に必要な3つの資格とは


弱電設備は生活や業務を支える重要な役割を果たすため、施工や管理には以下の資格が必要です。強電設備とは電圧や目的が違うので、必要な資格も異なります。
資格1|電気通信主任技術者
資格2|総合無線通信士
資格3|陸上無線技術士
それぞれの資格について、詳しく見ていきましょう。
資格1|電気通信主任技術者
電気通信主任技術者は、電気通信事業法により制度化した事業用電気通信設備の維持監督や運用などの管理業務を行うための国家資格です。電気通信主任技術者は総務省令で定めた技術基準を維持できるよう、監督責任者として配置されます。
資格2|総合無線通信士
電波法第40条第1号で規定された海上・航空・陸上の無線設備を操作できる国家資格です。グレードが第一級・第二級・第三級に分かれており、それぞれ扱える範囲が異なります。無線局で行える操作は、無線通信や電話の通信操作、通信業務、暗号業務などです。
資格3|陸上無線技術士
電波法第40条第4号に規定された無線設備の技術操作が行える国家資格です。第一級を取得すれば、ラジオ・テレビなどの放送局や大電力無線局、無線標識局など、幅広いステージで活用できます。第二級は無線設備の空中線電力による制限があります。
強電設備工事に必要な4つの資格とは


強電設備工事では電圧の高い電力を供給・制御するため、感電や火災を防ぐために徹底した安全管理が欠かせません。強電設備工事に必要な資格は、以下のとおりです。
資格1|電気工事士
資格2|電気主任技術者
資格3|電気工事施工管理技士
資格4|エネルギー管理士
それぞれの資格について、詳しく見ていきましょう。
資格1|電気工事士
ビルや工場、一般住宅など電気設備の工事や取り扱いに必要な国家資格です。第一種・第二種に分類されており、それぞれで扱える範囲が異なります。
第一種:第二種の範囲に加えて、最大電力500kW未満の設備
第二種:600V以下で受電する設備
資格2|電気主任技術者
電気主任技術者は、電気設備の保安・点検を行うための国家資格です。扱える事業用電気工作物の電圧によって、第一種・第二種・第三種に分類されています。厚生労働省の調査によると、電気主任技術者は電気工事士よりも高い収入が期待できます(※1)。
※1参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
資格3|電気工事施工管理技士
建設業法27条に基づく施工管理上の技術責任者に必要な国家資格です。仕事の規模によって1級・2級に分かれています。1級は専任技術者や主任技術者、監理技術者になれる資格です。一方の2級は、一般建設業の専任技術者または主任技術者になれます。
資格4|エネルギー管理士
省エネ法に規定された電気や熱エネルギーなどの使用量を管理するための国家資格です。エネルギーを使用する設備の維持管理やエネルギー使用量の監視、エネルギー使用の効率化などを担います。専門分野が熱分野と電気分野に分けられているのが特徴です。
弱電と強電を隔離すべき2つの理由


弱電と強電は隔離して使用しなければ、火災や誤動作につながる危険があります。離隔距離に明確な規定はなく、両者が直接接触しないことが条件です。保護管やセパレーターを使用して、弱電と強電を隔離しましょう。弱電と強電を隔離すべき理由は、以下のとおりです。
理由1|接触による混触を防ぐ
理由2|誘導障害を防ぐ
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
理由1|接触による混触を防ぐ
強電と弱電の接触による混触は最悪の場合に発火や火災につながるため、両者の隔離が必要です。強電側の地絡に弱電流電線との混触が発生した場合、弱電流電線には高い電圧が流れ、弱電機器が破損したり使用者が感電したりするリスクが高まります。
理由2|誘導障害を防ぐ
強電のケーブルには給電中に磁束が発生しており、誘導障害を防ぐために弱電と強電の隔離が必要です。弱電線と強電線が交差または平行にケーブルが走っている場合、電磁誘導作用により弱電ケーブル側に誘導電流が流れ、機器へのノイズが発生します。
ノイズは、通信エラーや機器の誤動作につながりかねません。弱電機器は微弱な信号を扱うため、僅かな干渉によっても信号品質が劣化する恐れがあるのです。
関連記事:白物家電と黒物家電の違いとは?代表例の一覧や白物家電の節電対策も解説
関連記事:50Hzと60Hzを間違えると?なぜ統一しないのかや周波数の違いも解説
弱電・強電両方に対応できるポータブル電源


自宅でコンセントの口数が少ない部屋や、災害による大規模な停電時に弱電・強電の両方を稼働するためには、ポータブル電源が必要です。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を貯めこみ、コンセントがない場所でも電化製品に給電できる機器を指します。
大規模な停電時にポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。
冷蔵庫に給電して、食品が傷むのを防ぐ
エアコンや扇風機などの冷暖房機器を稼働して、快適な気温を維持できる
電子レンジや電気ケトルを稼働して、簡単に非常食を温められる
LEDライトを点灯させて、夜の安全を確保できる
携帯ラジオを稼働して、最新の災害情報を収集できる
弱電の通信設備やLAN配線を稼働し、家族と連絡が取り合える
ポータブル電源にはコンセントと同様のAC出力やUSB-A、USB-Cなど、多彩な出力ポートを搭載しているので、家庭にあるほとんどの家電が動かせます。
弱電・強電設備の給電に必要な性能|おすすめの製品
DELTA 3 Max Plus(2048Wh)
最大出力3,000W、容量2,048Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大3,800Wの弱電・強電機器にも対応し、大家族の停電対策にも最適です。各ポート最大2,000W出力のAC出力ポートや、高出力のUSB-Cポートなど、合わせて計10の出力ポートを搭載しています。
4つのAC出力を2つに分けてコントロールできるので、夜はエアコンと冷蔵庫はオン、照明だけオフ、といった使い方が可能です。主要ポートは前面に集約しているので、スムーズに接続できます。X-Stream急速充電技術により、わずか108分で満充電が可能です。
DELTA Pro 3
定格出力3600W、容量4kWhのポータブル電源。エクストラバッテリーで最大12kWhまで容量を拡張できるので、停電生活が長期化しても安心です。X-Boost機能で最大5100Wの家電を稼働でき、200Vの強電機器にも対応しています。
UL94 5VA認証の難燃素材を採用し、独自の安全保護機能「X-GUARD」を搭載しているので、安全性も抜群です。ハンドル付きのコンパクト設計により、持ち運びも楽々。ソーラーパネルのデュアルPV充電により、停電中も最速2.2時間で満充電できます。
弱電と強電に関するよくある質問


最後に、弱電と強電に関するよくある質問を紹介します。
弱電において強電からのノイズ・干渉を防ぐには?
弱電と強電は同一配管に納めてもよい?
弱電工事と強電工事で扱う電圧は何ボルト?
それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。
弱電において強電からのノイズ・干渉を防ぐには?
弱電と強電の接触によるノイズ・干渉を防ぐ対策は、以下のとおりです。
ケーブルや機器を金属製のシールドで覆う
2本の電線を密接にねじれさせる
強電と弱電のケーブルを離して配線する
システムを適切に接地する
中でもアース(接地)は、ノイズ対策だけでなく安全対策としても効果があります。
弱電と強電は同一配管に納めてもよい?
基本的に弱電と強電の配管は別々に敷設した方がよいでしょう。ただし、やむを得ずに弱電と強電を同一配管に納める場合は、以下のポイントに注意が必要です。
弱電流電線に絶縁電線と同等以上の絶縁効力を持つものを使用する
配線との識別が容易にできるものを使用する
弱電流電線はリモコンスイッチ用や保護継電器用に限る
電話線やインターホン用弱電流電線は含まれない
C種設置工事を施したシールドアースを有する通信用のケーブルを使用する場合は、同一配管に納めて問題ない
弱電工事と強電工事で扱う電圧は何ボルト?
弱電工事の使用電圧は48ボルト以上、強電工事は100V以上です。強電工事では大型機械や発電所などの高い電圧を扱うため、より徹底した安全管理が欠かせません。弱電工事と強電工事で必要な資格は異なるので、注意しましょう。
まとめ


本記事では、弱電や強電とは何かについて解説してきました。
弱電は情報の伝達や制御が目的の電気で、48V以下の電圧を持ちます。一方の強電は動力やエネルギー源として使用され、100V以上の使用電圧があります。弱電設備の具体例は、通信設備や放送設備、LAN配線など、強電設備はエレベーターやコンセントなどです。
強電設備工事では電圧の高い電力を供給・制御するため、弱電設備工事よりも専門性の高い資格を取得する必要があります。弱電と強電を使用する際は、接触による混触や誘導障害を防ぐために両者を隔離しましょう。
EcoFlowは、弱電と強電の両方に対応できるポータブル電源を販売しています。コンセントの有無に関わらず、あらゆる家電を動かしたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。