スキーブームの隆盛と衰退の流れ!現代スキーの新たなブームについて解説
スキーは、日本の高度経済成長期やバブル期に社会現象となるほどの盛り上がりを見せ、若者やファミリー層を中心に多くの人がゲレンデを訪れていました。
しかし、バブル崩壊や少子化、ライフスタイルの変化、暖冬や雪不足などの要因が重なり、その勢いは次第に衰退していきます。
一方、近年ではコロナ禍を経たアウトドア人気やインバウンド需要の高まり、SNSを意識した楽しみ方の拡大などで、再び現代的なスキーブームの兆しが見えています。
この記事では、過去から現在までのスキーブームの隆盛と衰退の歴史、現代的な新たなムーブメントについて詳しく紹介します。
スキーブームの歴史的な流れ
スキーブームの歴史は、社会的背景は技術の進化とともに衰退を繰り返しています。ここでは、ブームの歴史的な流れについて詳しく解説します。
戦前~戦後:第一次スキーブーム
日本のスキーブームの始まりは、戦前の1930年代まで遡ります。
リゾートホテルの建設や国策によるスキー普及活動が各地で活発化し、山岳スキーが都市部の若者や軍人を中心に流行しました。
この頃、山岳地ではリフトの整備が進まずスキー板を担いで山を登るのが主流でした。戦中は一時低迷しますが、戦後は観光施設の拡充が進みレジャーとして定着します。
地方の民宿や温泉ホテルに泊まりながら、グループや家族連れがスキー旅行を楽しめる環境が急速に整っていったのがこの時代です。
高度成長期:第二次スキーブーム
第二次スキーブームは、1960〜70年代の高度成長期です。
週休二日制の普及と交通インフラの整備が追い風となり、余暇を楽しむレジャーとしてスキー人口が爆発的に増加しました。
また、新幹線や高速道路の開通で都市部からのアクセスが良くなり、スキー周辺にはペンションや民宿が建ち並び始めます。
1972年には札幌オリンピックが開催され、日本人選手が金メダルを獲得したこともブームの火付け役となりました。
スキーは若者を中心に社会的な流行となり、多くのスキー場が新設されます。
バブル期:第三次スキーブーム
第三次スキーブームは、1980年代後半から1990年代前半のバブル期です。
消費意欲の高まりや大規模な交通網の発達、映画やキャンペーンなどメディアの影響で、スキー人口が急激に増加しました。
最盛期の1993年にはスキー産業がピークを迎え、経済成長とともにスキー用品や施設の多様化も進み、仲間や企業のグループ旅行が定番化します。
ただし、バブル崩壊後は消費の減退やライフスタイルの変化により、スキーブームは徐々に落ち着きを見せていきます。
2010年~:スノーボード普及やインバウンドの増加
2010年代以降は、スノーボードの人気拡大や外国人観光客(インバウンド)の増加が新たなブームの要因になっています。
コロナ禍を経た世界的なアウトドアブームや、SNS映えを意識したアクティビティ展開を背景に、国内外の新しい層がスキー場に足を運び始めています。
日本のスキーは社会情勢や文化の変化に合わせて、ブームの形も柔軟に変化しています。
スキーブームが起きた社会的要因
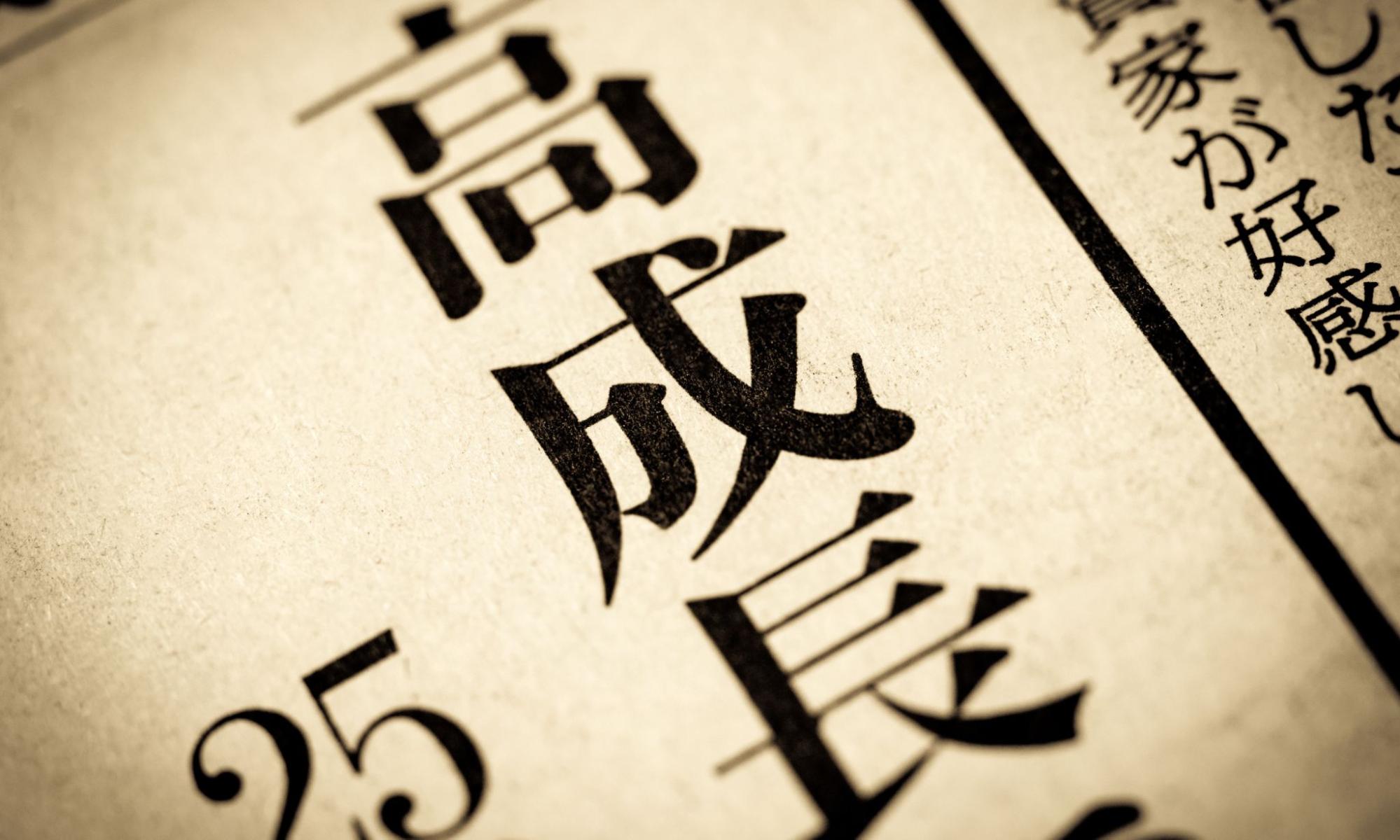
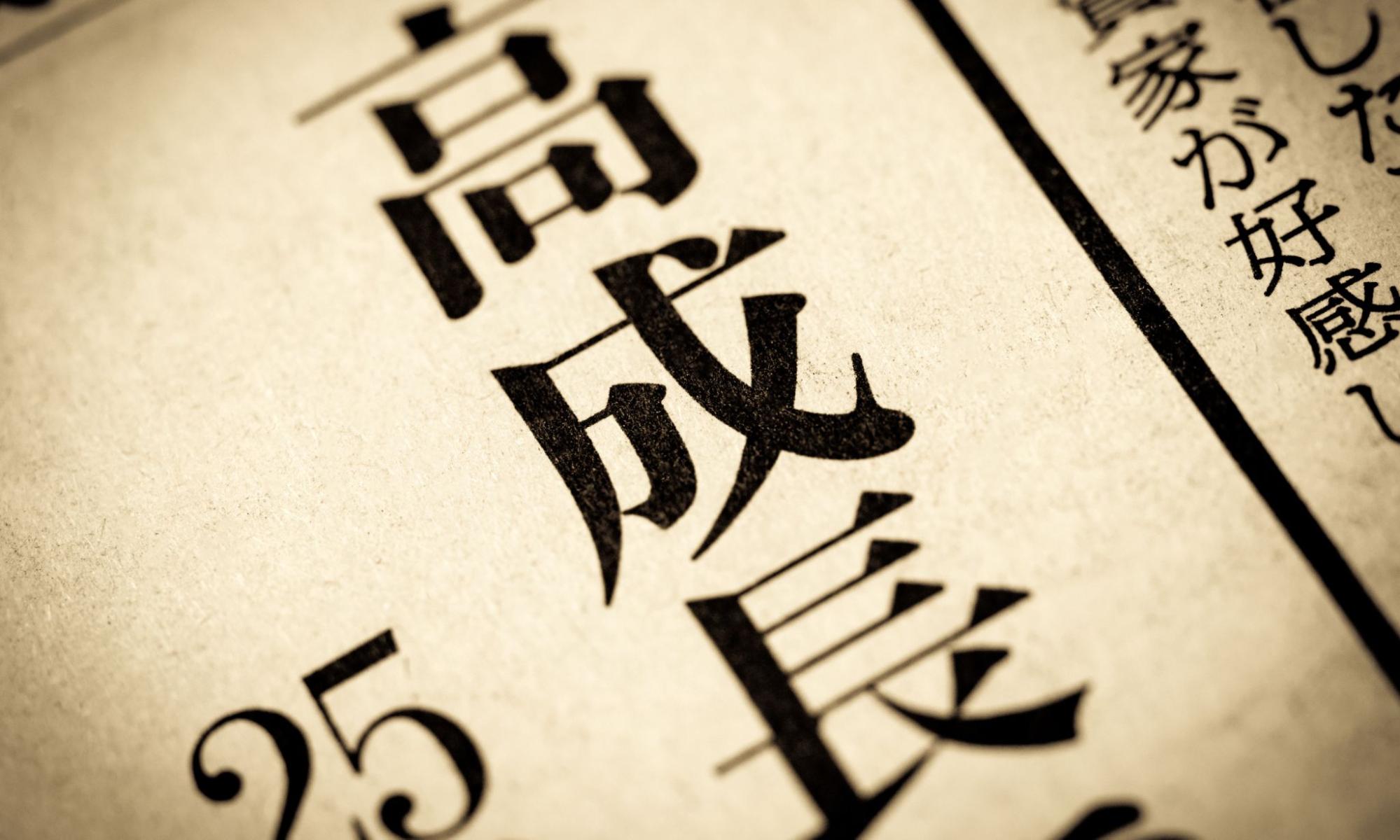
日本のスキーブームは、様々な社会的環境と重なり発生しました。ここでは、ブームが起きた要因について詳しく解説します。
経済成長と可処分所得の増加
戦後の高度経済成長期は、所得水準が上昇したことで家計の可処分所得も増加しました。
その結果、日本人に余暇を楽しむ文化が広がり、マイカーやカラーテレビの普及と相まってレジャーや旅行への関心が高まっていきます。
スキー用品の価格低下や量産化が進み、一般家庭でも手軽にスキーを体験できるようになったことも大きな要因です。
バブル経済の影響もあり、冬のレジャーとしてスキーに多くの予算を割くことができるようになり、スキー場やリゾート施設への投資が盛んに行われました。
交通インフラ整備によるアクセス向上
交通インフラの発展は、スキー人気を爆発的に押し上げた大きな要因です。
新幹線や高速道路の整備、スキー列車や格安ツアー券の発売などで、都市部からスキー場までのアクセスが劇的に向上しました。
また、旅行代理店がセット商品を強化したことで、団体や家族旅行など、様々な層が気軽にスキーを楽しむ環境が整備されたこともポイントです。
企業や学校のレクリエーション化
企業や学校が、福利厚生やレクリエーション活動の一環でスキー旅行を積極的に導入し始めたことも、スキー人口増加の大きな要因です。
修学旅行やサークル活動、社員旅行としてスキーを取り入れるケースが増え、団体割引や特別パックも広まりました。
職場や学校単位でのレジャーが定着したことで、スキー場には多様な世代や職業の人が集うようになり、ブームの広がりを生み出したのです。
メディアや映画がスキーを流行にした
スキーブームのきっかけとして、メディアや映画の影響力も無視できません。
1960年代の『アルプスの若大将』や、1987年公開の『私をスキーに連れてって』といったヒット作品は、多くの若者にスキーの楽しさを訴求しました。
テレビや雑誌はスキー場の魅力や流行のウェアを紹介し、さらに皇族がスキーを楽しむ姿やオリンピックの盛り上がりがブームに拍車をかけます。
これらのメディアの効果によって、スキーは一時的な流行ではなく文化として根付くことになったというわけです。
スキーブームが衰退した理由
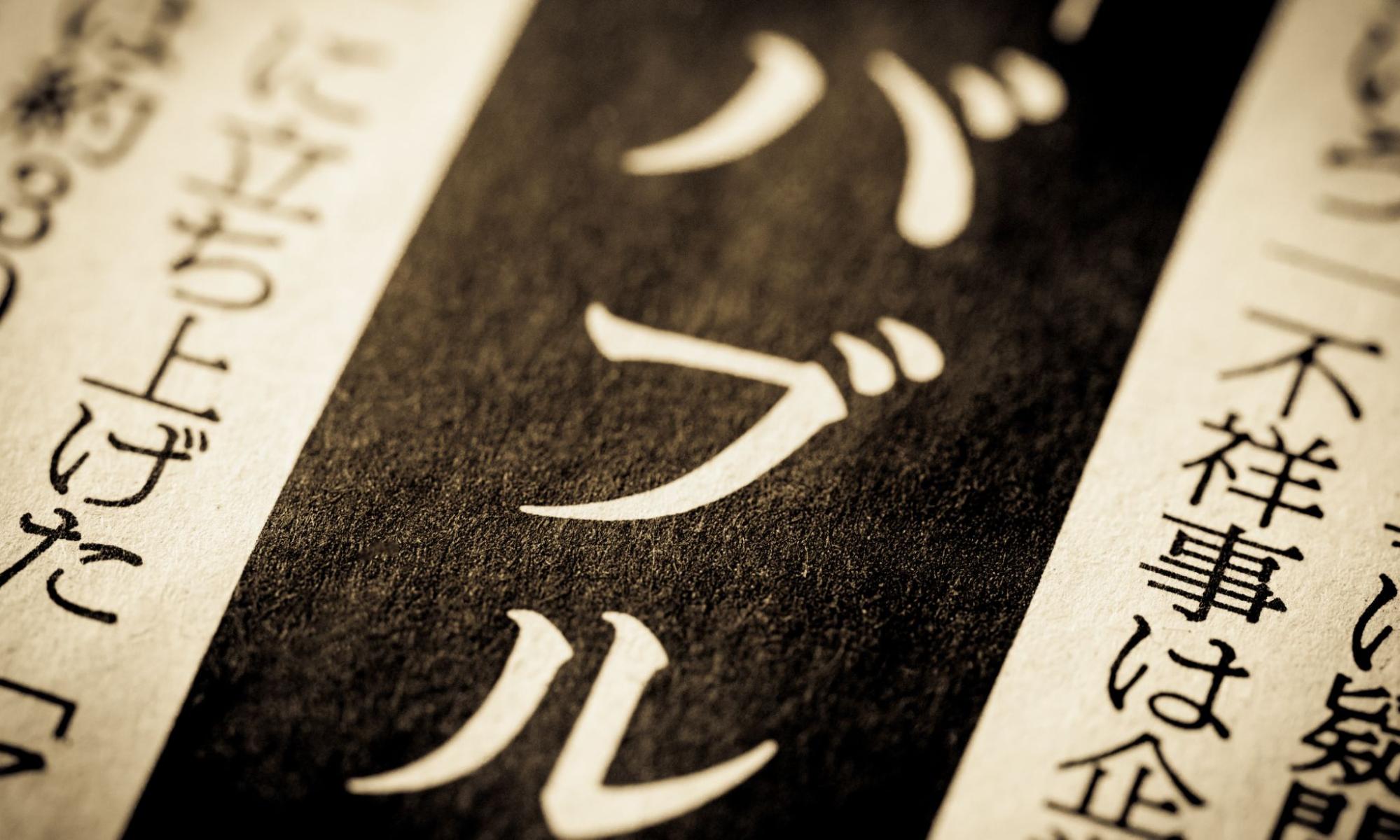
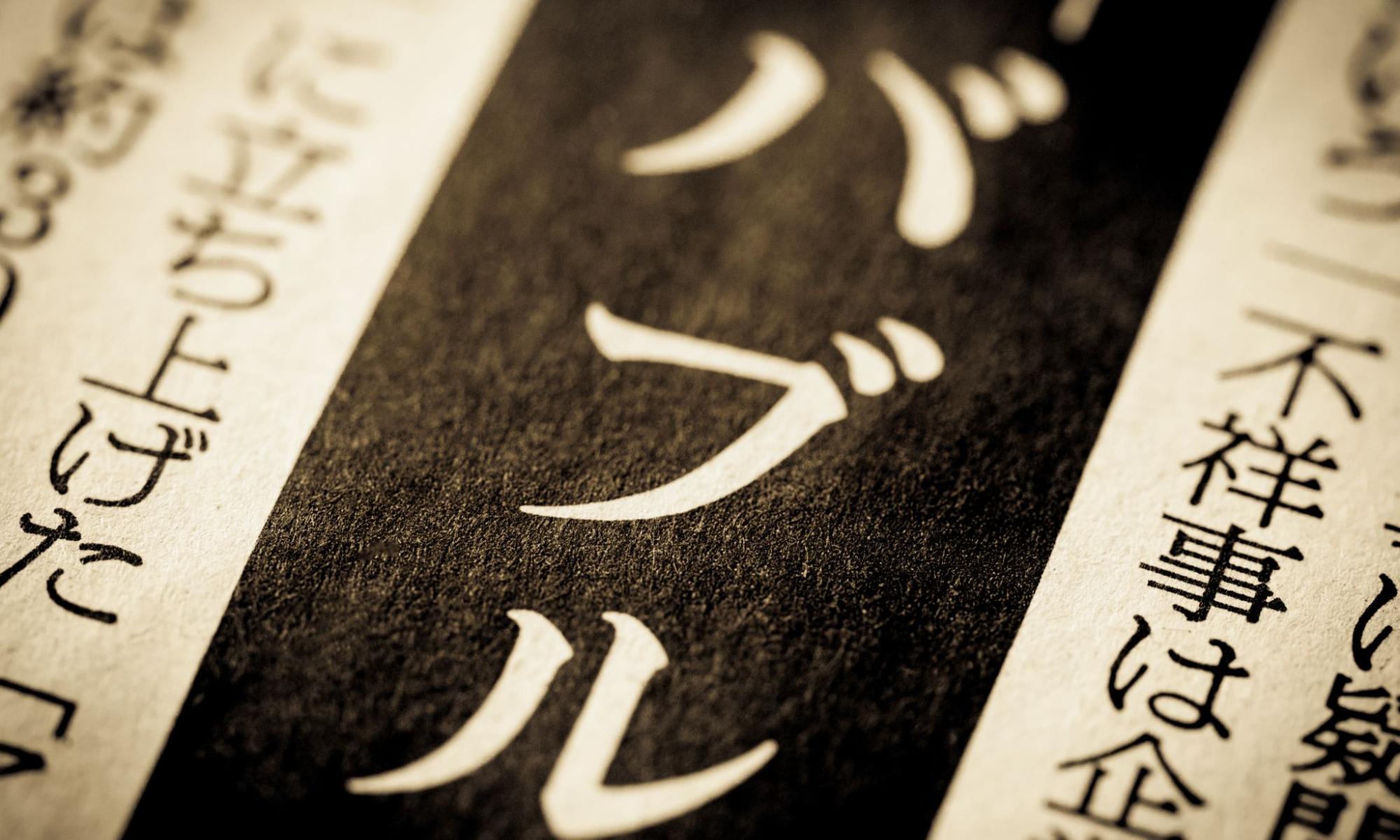
スキーブームの陰りは、様々な社会的要因によってもたらされました。ここでは、主な理由について詳しく解説します。
スキー場の過剰供給
スキー場の過剰供給により、日本全国で経営の競争が激化しました。
バブル期のピーク時には全国に700以上のスキー場がありましたが、スキー人口の減少とともに利用者数が低下し、赤字や廃業に追い込まれていきます。
投資回収が困難になり、サービスや施設改修も停滞したことで全体の魅力が低下。スキー場の廃業が相次いだことで、スキーブームの衰退は加速したのです。
若年層の嗜好変化と少子化
若年層の消費行動や価値観の変化は、スキー人気の減退に大きく作用しています。
例えば、スマートフォンやSNS、都市型娯楽や海外旅行など、様々な選択肢が若者の冬の過ごし方を多様化させました。
さらに、人口減少と少子化が進み、修学旅行や家族旅行という集団利用型の需要が著しく減少したことも大きな要因です。
客層の高齢化やリピーターの減少も重なり、スキー離れが顕著となりました。選択肢が増えたことで、かつてのようなブームを維持することは困難になっています。
維持コスト上昇と代替レジャーとの競合
スキー場の運営には、設備維持やエネルギーコストなど高額な経費が必要ですが、近年は特に原材料費やエネルギー高騰の影響で負担が増しています。
リフトや雪上車、降雪機の更新、施設の改修にも多額の投資が求められる一方、家計や企業の支出減少で高額なレジャーへの消費は控えられています。
さらに、テーマパークや都市型商業施設、海外旅行など消費者の選択肢が増え、スキー場はかつての集客力を失いました。
経済環境の変化と他分野の競争が、施設運営の難しさを増大させ、産業の縮小を招く要因となったのです。
暖冬や気候変動による雪不足
近年の気候変動による暖冬や異常気象は、スキー場の積雪量を減少させ、営業期間短縮や品質悪化をもたらしています。
積雪不足は、人口降雪機の稼働や追加の設備投資を必要とし、結果として運営コストも増大します。
雪質や積雪量への期待が裏切られることで、利用者の満足度やリピート率が低下し、安定した集客が困難となっている状況です。
スキー場にとって致命的でもある雪不足も、衰退した理由の一つに挙げられます。
現代スキーの新たなブームについて


スキー業界は過去のブームの盛衰を経て、近年は新たな社会的トレンドの波を受けながら明るい兆しを見せています。
ここでは、現代スキーの新たなブームについて解説します。
インバウンド回復による外国人需要の増加
近年、日本のスキー場ではインバウンド観光客の増加がかつてないほど顕著です。
円安やコロナ明けでの国境再開、世界屈指のパウダースノーや温泉、食文化の魅力が評価され、欧米やアジア各国からの訪日スキーヤーが急増しています。
ニセコ・白馬・富良野などのリゾートは長期滞在・周遊型観光も定着し、多言語対応やレンタルサービス、パッケージプランなど受け入れ態勢も強化されています。
インバウンド需要の高まりが、スキーブームを新たなステージへと押し上げているのです。
SNSや体験重視の観光トレンドが話題を促進
体験型消費が若者層を中心に広がり、SNSでの発信が新しいブームや人気スポット創出の原動力となっています。
スキーシーンを動画や写真で映えさせたり、体験をSNSで拡散することで、非日常的な冬のレジャーを気軽に共有できる時代となりました。
従来の『滑る』消費だけでなく、『体験』や『参加』そのものが、現代のスキーブームの中心となりつつあります。
コロナ後のアウトドア志向と若年層の回帰
コロナ禍を経て、屋外でのレジャーや安全な体験への志向が高まりました。
特に2020年代以降、健康志向や自然とのふれあいを重視する若い世代が、スキーやスノーボードへ回帰しつつあります。
さらに、最新機器やレンタル用品の充実によって初心者も気軽に参加でき、幅広い層の取り込みにつながっています。
関連記事:スキー板の長さを決める基準は?操作性の違いや正しい選び方を紹介!
関連記事:スキーのパラレルターンとは?上達する練習法や実践テクニックを紹介!
スキーブームを支える便利アイテムはこれ!


スキーやスノーボードを楽しむ現代のゲレンデライフには、スマートフォンやカメラ、ウェアラブル機器など様々なデバイスの充電が欠かせなくなっています。
そこで注目されているのが、EcoFlow RAPID Power Bank(25,000mAh, 170W, USB-Cケーブル内蔵)です。
大容量25,000mAhと最大合計170Wの高出力を実現し、USB-CとUSB-Aをあわせて同時に4台までの機器を急速充電できます。
内蔵USB-Cケーブルは100Wの高速伝送に対応し、ノートパソコンや最新スマートフォンにも安心して使える安心設計です。
また、カラーディスプレイでバッテリー残量や出力状況を一目で確認でき、過充電・過熱・過放電・異常電圧時の保護機能も搭載しています。
ただし、マイナス10℃以下になると自動的に保護モードになり、バッテリーの出力が制限されるため、スキー場での使用は注意が必要です。
日本国内の多くのスキー場(標高2000m未満・外気温-10℃程度)であれば通常通り使用可能ですが、高山や極端な寒波時の屋外使用は避けましょう。
スキー場での快適な滞在や撮影だけでなく、緊急時のライフライン確保にも使えるため、ぜひ今年のスキーでは持参してみてください。
スキーブームに関するよくある質問


最後に、スキーブームに関するよくある質問を詳しく解説します。
スキーブームのピークはいつ?
スキーブームの最盛期は1993年頃で、過去最大の盛り上がりを見せました。
バブル景気や大規模な交通インフラの整備、映画『私をスキーに連れてって』などのヒットが重なり、スキー人口は1860万人まで膨れ上がりました。
この時期、臨時スキー列車「シュプール号」の運行や、高速道路・新幹線の開通も追い風となり、ゲレンデは若者や家族連れで溢れていました。
スキーブームはまたくる?
新たなスキーブームの兆しは、近年のインバウンド需要拡大や若年層のアウトドア志向の高まりを背景に確実に広がっています。
特に2020年代以降、SNSの普及や体験型消費、外国人観光客による需要増加が、ゲレンデの賑わい回復に大きく貢献しています。
また、サービスの多様化や設備改修、環境整備が進み、家族や初心者も楽しみやすくなったこともブーム再燃を支える要因です。
今後はインバウンド対応や体験重視、安全面の向上など、様々な切り口でさらなる成長が期待されます。
まとめ
スキーブームは時代ごとの社会背景やブームの波を経て、形を変えながら今日まで発展と停滞を繰り返してきました。
1990年代の絶頂期をピークに一度は減少傾向となりましたが、2020年代以降はインバウンド観光客やアウトドア志向の高まりによって、再びゲレンデに活気が戻っています。
現代のスキー場は過去と異なる新しいブームを牽引しており、時代に合わせて形を変えながらこれからも進化を続けていくでしょう。
また、時代の変化に欠かせないアイテムがモバイルバッテリーです。雪山でデジタル機器を安心して使いたいスキーヤーは、ぜひチェックしてください。